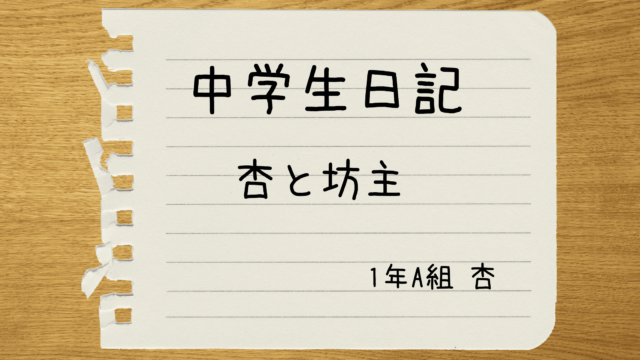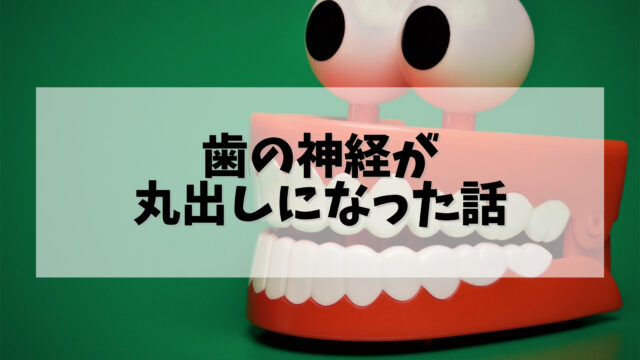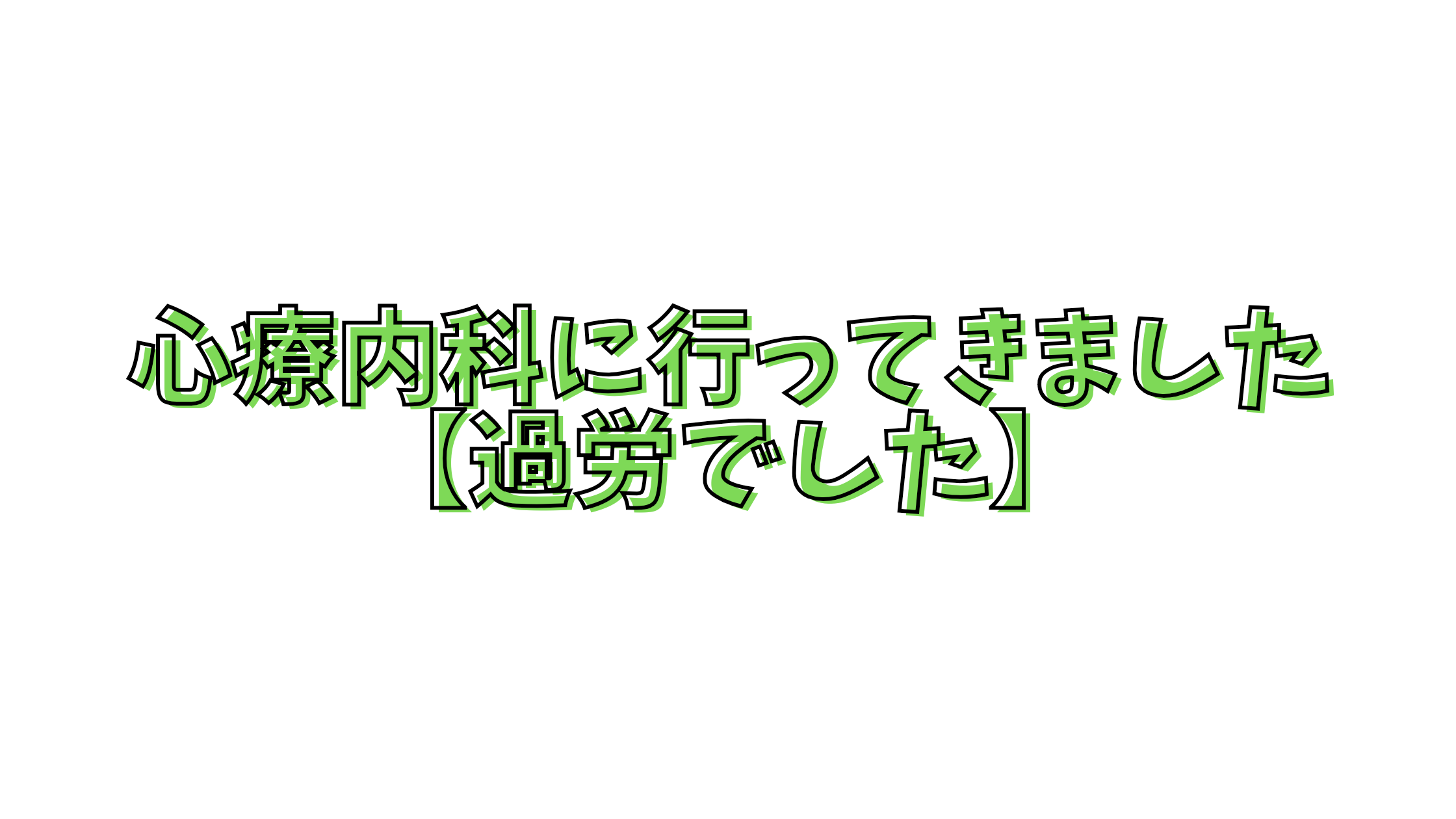いやぁ〜〜〜〜。なんだか久しぶりにブログ書いてます。
最近簿記の勉強に時間を取ってたので全然時間なくて…ブログスタートしてから初めてじゃないかな??1週間以上投稿があいちゃいました。
もうね、それくらい難しかったんですよ。簿記。
今日は朝から3級の試験を受けてきたので、その感想を書きたいなと思います。
その前に、今日簿記3級を受けた同志の皆様本当にお疲れさまでした!!
何がとは言いませんよ…あの問題を見た人なら頷いてくれるはず。
簿記3級の試験、難易度は?

難しかったです。普通に。
ただもっと難しいのを想像しながら問題を見たので衝撃は少なかったですね(汗)
クレアールの模擬試験問題を解いてなかったら頭真っ白になってたと思います。
解けるかどうかは別としていい意味で難しい問題に免疫がついていた事もあって、最後の最後まで戦意喪失することなく頑張れました!
【簿記3級今回からの試験条件】
試験時間:60分(前までは120分)
大問1:仕訳問題15問、計45点
大問2:何が出るかな?2問、計20点
大問3:決算系1問、計35点
大問2が鬼門でしたね…
一瞬見ただけでパスして大問3に進みましたもん。
私はてっきり伝票とか商品有高帳が来るものとばかり思ってね、昨日も寝るギリギリまで最後の悪あがきをしてたんです。それなのに。
こんなのを3級でやるとは思いもしませんでした。簿記の神様がもしいるなら追いかけ回して髪の毛根こそぎ引きちぎってやりたい。
…冗談はさておき。
結果的に大問2以外は結構解けたんですよ。
惑わせるような言い回しをするところとかもあったりはしたけど、大問3も最後まで埋められましたし。
6月28日?29日?以降に結果発表があるようなので楽しみにしたいと思います。自信はないですけど、想像してたよりもパッションを見せられたので合格でも不合格でもいい経験になりました!
独学で簿記3級検定を受けて感じたこと
- 教材選びの大切さ
- 試験当日までの勉強時間の配分が難しい
- 大問1→3→2の順番で解く
教材選びの大切さ
学校に行って教えてもらうのとは違って、独学だと教材を見つけるところからしないといけないっていうのがまず大変。
私はYouTubeで両学長さんの動画を見ている時におすすめで出てきたクレアールという会社の教材を選ぶことに。
配信の講義動画を見ながら問題を解いたり書き込みしたり、過去問も送られてきたのでそれを解いたり。やっぱり動画って良いですね。自分だけでテキストを読むよりも解説が入ると集中しやすいというか。
あとクレアールオリジナルの試験対策問題が4冊くらいあるんですけど、それが極悪級の難しさなんですよ…
1週間前に心折れました…未だに60分で解けないんです。ていうかまず間違えまくり(汗)
でもその問題を見慣れていたからか、今回の試験問題の独特な言い回しも落ち着いて考えることができたように思います。
本屋さんで売っている本とかYouTubeの動画だけだと、基礎的な問題は解けても日本語で攻撃してくるタイプの応用問題に対応できない気がして。
イジワル問題が出ても怯まないメンタルを手に入れられるのがクレアールの大きなメリットかなと思います。
試験当日までの勉強時間の配分が難しい
【おすすめの時間の使い方】
試験3ヶ月〜3週間前:基礎知識を身につけるための勉強。
試験3週間前〜当日:過去問や対策問題を時間を測りながらひたすらに解く。
教材選びは良かったんですが、私の時間の使い方が下手くそすぎました。
クレアールの講義動画ばかり見て過去問を解いてなかったんです。動画を見て分かった気になっても、実際に解いて正解するかはまた別のお話で。
それを分かってなかったんですよね。
1週間半前に初めて過去問を見て焦りました…過去問(120分)と対策問題(60分)の表紙の制限時間を見て、今回の試験時間が短縮されたことにやっと気付く私。
とりあえずやってみましたけど精算表やら損益計算書らへん、ほぼ手を付けられなかったんです。
今思えば最低でも2週間以上前から過去問や対策問題に集中するべきでしたね(汗)
ある程度文字を埋められるようになる頃にはもう試験2日前。笑うしかない…
60分の対策問題は鬼のように難しいし。何度諦めてふて寝しそうになったことか。
最後は諦めて大問1の仕訳15問を1問あたり1分で解く練習をしてました。これが良かったのか、格段に解答スピードが上がったんです。
試験前日には鬼ムズ対策問題の仕訳15問を約12分で解けるようになって、精算表は25分以内で解けるように。
多分これくらいのスピード感じゃないと最後まで問題に目を通せずに終わります。
ただ精算表の貸借対照表と損益計算書の最終の書き分けが全くできないままでした…
スピードだけは自信がついたので、最後に勘定科目の分類を改めて書き出して枕の下に入れて寝ました(笑)
本当なら1つ1つ暗記じゃなくてその場でさっと仕訳できるようにならないといけないんですけど、そんな時間もなかったので…荒療治です。
最低限のところだけ覚えて、あとは記憶から消しました。
仕訳ができずに検定当日を迎えそうな人の緊急の覚え方
「精算表」が試験に出たら、訂正仕訳後とりあえず「現金」科目から順番に右端の列に書いていく。「売上」科目から下は「損益計算書」の列(左の列)に書く。
決算整理で追加された科目を書き分ける時↓
貸借対照表に仕訳する「資産」「負債」「純資産」の勘定科目はたくさんあるので意識しない。
損益計算書の「収益」と「費用」の勘定科目はそこまで多くないのでそちらだけ覚える。
「収益」に分類される勘定科目には、受取とつくものが入る。(受取利息・受取家賃など)
「費用」に分類される勘定科目には、支払、〜費とつくものが入る。(法定福利費、支払利息など)
前受や仮払、未払などの「払った払ってない」がややこしい勘定科目は全て貸借対照表行きになる。(精算表の右端の行に書く)
最低限これだけ覚えてたら勝ち。
あとは電卓の打ち間違いやイジワル問題の日本語に惑わされなかったら最高って感じで。
大問1→3→2の順番で解く
制限時間60分。見直しをするような時間はない真剣勝負。
配点が多い順番に解くべきです。
対策問題の時も感じたんですが、イジワル問題の読み取りに時間をかけるのはダメなんですよね。特に出題範囲が広すぎて対策しようのない大問2。
ヤツに時間をかけ過ぎて大問3を全て埋められずタイムアップで大量減点を何回か経験したので、本番で大問2から嫌な匂いがプンプンするのを見逃すことなくスキップ。
おかげで大問1を15分以内、大問3を25分くらい、大問2に20分以上時間をかけることができました。って言っても根性で埋めただけですけど。
付け焼き刃ではダメだし、単純な問題ばかり解いててもダメってことですね…不合格ならもう一度勉強し直して、次はネット試験でも挑戦してみようと思います。
あ!!忘れてたけど、ひとつだけ困ったことがあったんですよ。
問題用紙と解答用紙と計算用紙で1つの冊子になってるんです。しかも計算用紙は一番最後の見開き2ページくらい。どうやって使うねん!!!
問題解きながらペラペラ紙めくって鬱陶しい。あれは絶対に改善するべき。計算用紙は別にしてほしいです。
制限時間60分で難しい問題出して、メモしにくい位置に計算用紙つけるってどない??
私は諦めて問題用紙の隙間にいっぱい書き込みました。
そう、計算用紙のことだけは言っときたかったんです。次の統一試験受ける方の時はどうなるか分かりませんが、今回はそんな感じでした!
色々ありましたが、伝説の第158回簿記3級検定を受けられてよかったです。楽しかった!!
それでは今から我慢してたルーンファクトリー5をやろうと思います。
今日は本当にお疲れさまでした。
おしまい
▼▼ブログ村ランキング参加中。ポチッと応援よろしくお願いします!▼▼